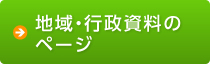[ここから本文です。]
地域に関するレファレンス事例集
[ここから本文です。]
分野別インデックス
- 40妙見信仰と千葉氏について知りたい
- 39稲毛あかり祭り(夜灯)について知りたい。
- 38土気城について知りたい。
- 37稲毛海岸にあった日本初の民間飛行場について知りたい。
- 36誉田飛行場について知りたい。
- 35千葉県の郷土料理について知りたい。
- 34千葉県で過去に流行した感染症(疫病)に関する資料を見たい。
- 33検見川送信所(検見川無線送信所)の歴史について知りたい。
- 32稲毛にある「明治天皇御野立所(おのだちしょ)」の碑や歴史について知りたい。
- 31丹後堰の歴史について知りたい。
- 30稲毛浅間神社について知りたい。
- 29千葉駅(JR)の歴史について知りたい。
- 28千葉市の地名の由来について知りたい。
- 27千葉市の海岸の変遷(昭和以降)について知りたい。
- 26高校野球に夏の千葉県大会で戦後の優勝校(甲子園出場校)が、どの高校か知りたい。また、一覧表があれば見たい。
- 25千葉寺の戻り鐘の伝説について知りたい。
- 24千葉市が被害を受けた空襲について調べたい
- 23千葉市の各行政区の名前(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)が決まった経緯を調べたい
- 22妙見大祭について
- 21稲毛区黒砂あたりに川が流れていたのか知りたい
- 20大賀ハスは食べられますか?
- 19千葉常胤(つねたね)について知りたい。
- 18稲毛にあった「海気館」にどんな人が泊ったのか知りたい。
- 17最近千葉市に引っ越してきたのですが、自分の住む区のことを知りたいです。何か便利な資料はありますか。
- 16加曽利貝塚(千葉市若葉区桜木町)について知りたい。
- 15こじま公園(美浜区高洲)にあった海洋公民館について知りたい。
- 14矢作トンネルの上にある高架水槽について知りたい。
- 13千葉市の人口が知りたい。
- 12大賀ハスを発見したときの資料を探しています。
- 11江戸時代、印旛沼の水を、花見川から東京湾へ流す掘割工事があったというが、どのような工事だったのか。
- 10都川について調べたい。
- 9千葉市にあった城などについて調べたい。
- 8「絶滅危惧種」について調べたい。特に千葉県内の絶滅危惧種に関する資料はありますか。
- 7子どものころ(戦前)に稲毛あたりの海岸で潮干狩りをした記憶があるが、
その頃の稲毛海岸の写真などが紹介されている本がみたい。 - 6御成街道について調べたい。
- 5千葉市の社寺、仏像について調べたい。
- 4千葉を襲った地震・台風など自然災害について知りたい。
- 3君待橋の由来について知りたい。
- 2千葉市の鉄道第一連隊について知りたい。
- 1千葉県内の企業の資本金や業績等について調べたい。
※回答に使用している参考資料の所蔵状況や貸出できるかどうかは、図書館ごとに異なります。所蔵状況等を確認するときは、資料名をクリックするかこちらの所蔵資料検索をご利用ください。
- 40妙見信仰と千葉氏について知りたい。
-
妙見は、北極星や北斗七星を神としたものです。また、仏教と一体化して妙見菩薩とも呼ばれ、天空から人を見守り、方角を示し、人の運命を司る神として信仰されました。そのような中で千葉氏は、勝利に導いてくれる神と
して信仰しました。
千葉氏の関係者が編さんしたといわれる『源平闘諍録』には、北の空にあった妙見が戦場に現れ、勝利を導く軍神として描かれています。そこでは千葉の妙見は、甲冑をまとい、剣を持つ勇壮な姿で現れます。北条氏に滅ぼされ、領地を奪われた千葉氏が、この危機を乗り越えるため、妙見を軍神とすることで一族の団結を図ったと考えられています。
このように、千葉氏は妙見を厚く信仰したため、かつて千葉氏の領地であった地域には、妙見をまつった神社が多く見られます。- 《参考資料》
- 『千葉氏入門 Q&A』千葉市立郷土博物館(2019)P12
- 『千葉氏と妙見信仰』岩田書院 (2013)
- 『千葉一族入門事典』啓文社書房 (2016) P121~132
- 『千葉一族の歴史』戎光祥出版(2021)P156~197
- 『妙見信仰の民俗学的研究』青娥書房 (2020) P121~130、P174~222
- 『妙見信仰と羽衣伝承』千葉市立郷土博物館 (2007)
- 『妙見信仰調査報告書 [1] [2][3]』千葉市立郷土博物館 (1992~1994)
- 『史料が語る千葉の歴史60話』 三省堂 (1985) P64~67
- 『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』 千葉市 (1974) P368~383
- 『千葉県の歴史 別編 民俗1』 千葉県(1999) P379~P384
- 39稲毛あかり祭(夜灯)について知りたい。
-
「夜灯(よとぼし)」とは、もともと稲毛で行われていた漁の名前で、現在は、「稲毛あかり祭 夜灯」として地域を盛り上げるお祭りとして開催されています。
このお祭りは、かつて稲毛海岸が遠浅だった頃に行われていた「夜灯漁」の風景を再現しようという試みから始まりました。
このお祭りが最初に開催されたのは、2006年12月21日~23日でした。
稲毛せんげん通りの商店街の人々と学生の会話から、この夜灯漁を現在の稲毛の街で再現するというアイデアが生まれ、千葉県商店街地域連携モデル事業の助成を受け、「第1回 稲毛あかり祭(夜灯)」を開催しました。
現在の主なイベントとして、稲毛公園を中心に竹灯籠やキャンドルなどで公園内をライトアップしています。灯篭は稲毛の幼稚園、小学校、中学校、老人会の方々が全て手作りしています。約2,000個の灯籠が会場を彩り、その一つ一つに地域の子供たちや住民が描いた絵が灯ります。
なお、このお祭りは毎年11月中旬から下旬に開催しています。
点灯時間は17時~20時です。入場無料です。- 《参考資料》
- 『稲毛あかり祭 夜灯(よとぼし)』(ファイル) 夜灯実行委員会(2023)
- 『千葉市いなげ「夜灯」(よとぼし)祭』 千葉大学社会学研究室(2011)
- 『ちばの樹 ひろがる千の葉』千葉大学文学部行動科学科社会学研究室(2011)P70~116
- 『ちばシティガイド』(ファイル) 千葉市観光協会(2010)
稲毛浅間通り商店街~稲毛あかり祭「夜灯(よとぼし)」 - 『mi-ru-to 稲毛区』 ゼンリン (2011)P7
- 『千葉市Walker』 角川マーケティング(2010)P69
- 『全国お元気商店街百選』 明治書院(2010)P35
- 38土気城について知りたい
-
伝承によると、土気城は奈良時代の726(神亀3)年、鎮守府将軍大野東人が蝦夷征討の軍事拠点として、砦を築いたのが始まりと言われています。また室町時代には千葉氏の支族土気太郎が館を構え、戦国時代には畠山重康の居城であったこともあるといわれています。その後、1488(長享2)年に酒井定隆が市内中野町の本城寺砦からこの城に移り、以降5代約100年間にわたって、この地域を支配しました。1590(天正18)年、豊臣秀吉の小田原征伐の時、秀吉の家臣浅野長吉に攻略されて滅亡しました。土気城は総面積15,000坪、本丸・二の丸・三の丸からなり、四重の堀に囲まれた難攻不落の名城といわれたそうです。近年、一の堀以北の本丸までの土地は民間企業に買収され、本丸址に土気城址の石碑が建っています。
- 《参考資料》
- 『わが街の旧跡を訪ねて 続 郷土史先生散策手帳〈ふるさと千葉の昔と今〉』和泉書房 (2014) P129~130
- 『むかしといまの土気 歴史と産業・文化』 武田文治/著 (2008) P42~53
- 『土気の歴史散歩』 武田文治/著 (2020) P104~108
- 『土気町周辺の散策』 千葉市立図書館・参考部会/編 (1985) P7~9
- 『千葉県の歴史散歩 歴史散歩 12』 山川出版社 (2006) P27~28
- 『日本城郭大系 6 千葉・神奈川』 新人物往来社(1980) P149~152
- 37稲毛海岸にあった日本初の民間飛行場について知りたい。
-
1910(明治 43)年日本で初めて飛行機が飛んだのは、東京の代々木公園にあった陸軍の練兵場でした。国家的プロジェクト「臨時軍用気球研究会」を発足させ、飛行機の研究に取り組んだ結果、初飛行を果たしました。研究会には、海軍技師の奈良原三次が参加しており、その後独立し、飛行機の製作に没頭します。代々木練兵場の初飛行の翌年、埼玉県所沢に陸軍の飛行場が開設され、「奈良原式2号機」を自ら操縦し、国産飛行機の初飛行に成功しました。その後、操縦を白戸榮之助に任せ、奈良原三次は機体の開発を続け、4号機の「鳳号」を完成させます。これらの活躍を新聞で知った伊藤音次郎は奈良原三次に熱烈な手紙を出して上京し、助手になります。所沢飛行場は輸入された機体が増えて研究活動ができなくなった奈良原三次は、移転を考えます。当時リゾート地でもあった稲毛です。遠浅の砂浜は、潮が引くと荷馬車が通れるほどになり、滑走路になると考えました。奈良原三次は、稲毛で常宿にしていた旅館「海気館」の主人に相談したところ、敷地だけでなく、丸太組の格納庫も建ててくれました。こうして、1912(明治 45)年、広い砂浜をそのまま滑走路に転用しただけですが、稲毛海岸に民間初の専用飛行場を開設することができました。奈良原一門である白戸榮之助は、民間操縦士第1号として賞賛され、教官として伊藤音次郎を教育しました。その後、独立した伊藤音次郎は、1916(大正 5)年に自ら作った「恵美号」で民間機として初めて東京や全国の訪問飛行に成功し、一躍飛行家として有名になりました。その後、1917(大正 6)年に台風による高潮に襲われ、飛行場は大被害を受けました。かつて、たくさんの飛行家たちが活躍した稲毛民間飛行場があった場所は、稲岸公園に整備され、飛行機の翼をあしらった「民間航空発祥之地記念碑」を設置しています。
- 《参考資料》
- 『稲毛海岸飛行場物語』千葉市みどりの協会 (2012)
- 『民間航空発祥の地 稲毛 100周年記念誌』千葉市みどりの協会(2013)
- 『歴史的資料で読み解く伊藤音次郎 明治末から大正・昭和、民間航空を愛し続けた飛行家の生涯』遊タイム出版 (2023)
- 『房総ヒコーキ物語』崙書房 (1985)
- 『空気の階段を登れ 黎明期にはばたいた民間飛行家たち』三樹書房 (2006)
- 『千葉市オーラルヒストリー 民間航空史編』千葉市中央図書館 (2024)
- 『男爵の愛した翼たち 上』日本航空協会 (2006) P46~83
- 『史料で学ぶ千葉市の今むかし』千葉市 (2022) P166~167
- 『千葉が誇る日本一 PART2 №19~№36』京葉銀行 (2015) №29
- 36誉田飛行場について知りたい。
-
現在の緑区平川町に造られた陸軍の飛行場です。
1943(昭和18)年に起工され、翌年1944(昭和19)年6月6日、誉田飛行場と命名されました。「滑空場(滑空訓練所)」とも呼ばれていたようです。予備学生及び少年航空兵が、グライダーで飛行訓練を行っていたほか、陸軍航空本部から実践配備もされていたようです。終戦後1948(昭和23)年に誉田飛行場は、帰農者に開墾地として区画され、払い下げられました。その土地の一部は、農業外の用地として使用されるようになり、現在その辺りは、千葉市消防総合センターや千葉市水道局平川浄水場があります。- 《参考資料》
- 『あの頃の暮し』 誉田商店会 (2006) P59~62
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』 千葉市 (1993) P476~477
- 『千葉いまむかし No.3』 千葉市教育委員会(1990) P7
- 『幻の本土決戦 第1巻』 千葉日報社(1989) P457~P460 誉田滑空場
- 『誉田の歴史散歩』 武田 文治(2020) P17~18 平川滑空場(誉田飛行場)
- 『朝日新聞縮刷版 昭和18年3月〜4月』 日本図書センター(1990) 昭和18年3月19日 朝刊 P3(P101)
- 『誉田のあゆみ』 千葉市立誉田小学校(1974)巻末年表
- 35千葉県の郷土料理について知りたい。
-
千葉県は、太平洋や東京湾の海や川に囲まれており、温暖な気候で農業も盛んな県です。醤油や落花生の出荷額も日本トップシェアを誇り、酪農発祥の地として乳製品も多く生産されています。海の幸や里の幸に恵まれた千葉県では「なめろう」や「さんが焼き」、「太巻き祭り寿司」、「背黒イワシのごま漬け」、「落花生味噌」をはじめ、たくさんの郷土料理があります。
参考資料で紹介された資料の他にも請求記号「C596」の棚にも千葉県の郷土料理の資料を所蔵しており、料理の作り方や由来などを紹介しています。- 《参考資料》
- 『日本の食生活全集12 聞き書 千葉の食事』 農山漁村文化協会 (1989)
- 『ちばの郷土料理 再発見!』 千葉県農林水産部流通販売課 (2022)
- 『ちばのおかず』 開港舎(2014)
- 『毎日食べたい千葉ごはん』 TOブックス (2015)
- 『旬のレシピ ちばの味 春夏編』 千葉県総合企画部報道広報課 (2009)
- 『旬のレシピ ちばの味 秋冬編』 千葉県総合企画部報道広報課 (2009)
- 『新鮮丸ごと 千葉のさかな [2021]』 千葉県農林水産部水産局水産課 (2021)
- 『母と子の楽しい太巻き祭りずし作り方教室 改訂新版』 東京書店(2009)
- 『伝統の祭りずし美味しいヘルシー家庭料理』大和美術印刷(株)出版事業部うらべ書房(2015)
- 34千葉県で過去に流行した感染症(疫病)に関する資料を見たい。
-
2020年の年明けから始まった新型コロナウイルスの感染拡大は、いまだに我々
の生活に大きな影響を及ぼしています。こんな時だからこそ、過去に流行した
感染症(疫病)や、それに対する当時の行政や県民の対応を知ることは意義深い
ことではないでしょうか。
例えば『千葉県と疫病』には、大正期のインフルエンザ(スペイン風邪)流行時
に作成された啓発用ポスターが、カラーで掲載されています。マスクの使用や
うがい、患者の隔離、消毒や予防接種など、現在でも通じる感染症対策が当時
から推奨されていたことがわかります。
また『石のカルテ』には、感染症(疫病)の治癒や流行の終息を願って造られた
千葉県内の石仏などが多数紹介されています。千葉市では、生実神社(中央区
生実町)にある「十一面観音像(疱瘡守護尊像)」や、坂月神社(若葉区坂月町)の
「疫病神」などが当時の人々の想いを今に伝えています。- 《参考資料》
- 『千葉県と疫病』 千葉県文書館 (2020)
- 『千葉県伝染病史』 崙書房出版 (2004)
- 『石のカルテ』 崙書房出版(1993)
- 『千葉県の歴史 資料編 近現代7』 千葉県 P80~81
- 『千葉市史 第3巻 現代編』 千葉市 P382~384
- 『千葉市史 史料編10 近代』 千葉市 P331~343、P473~474
- 33検見川送信所(検見川無線送信所)の歴史について知りたい。
-
検見川送信所は、1926(大正15)年に検見川町に開局しました。
旧逓信省・日本電信電話公社(現在のNTT)の無線送信所です。
日本初の短波による標準電波の送信をはじめ、1930(昭和5)年に当時の内閣
総理大臣がロンドン軍縮条約締結記念放送で記念演説を行い、日本初の国際
放送を行った施設として知られています。
局舎は、東京中央郵便局などを手掛けた建築家の設計です。鉄筋コンクリート
2階建てで、大正末期の貴重な建築になっています。
短波業務の近代化や送信所付近の都市化問題等から、茨城県に新送信所を移し、1979(昭和54)年に閉局しました。
現在、敷地内は立入禁止ですが、建物は外から見ることは可能です。- 《参考資料》
- 『検見川無線史』 東京無線通信部 (1979)
- 『検見川無線の思い出』 菊谷秀雄 (1990)
- 『検見川無線のプロジェクトX』 検見川送信所を知る会(2009)
- 『ちば市史編さん便り NO.1(2008.10)~』(ファイル)千葉市立郷土博物館 №9 (2012) P1~3
- 『わたしたちのまち』 花見川地元を学ぶ会 (2021) P15、P65
- 『電気通信発展外史』 日本電信電話(1993) P46
- 『けみがわ 検見川郷土史』 検見川小学校同窓会(1992) P264~267
- 『千葉市史 第2巻 近世近代編』 千葉市(1974) P392~393
- 『名残り』 千葉市文化振興財団(1993) P150~153
- 『稲毛十話』 千葉市立稲毛中学校1年4組(1990) P47~50
- 32稲毛にある「明治天皇御野立所(おのだちしょ)」の碑や歴史について知りたい。
-
JR稲毛駅の東京寄りの高架下にある大通りから海側に約50メートル先の左側に「明治天皇御野立所」の碑があります。 (稲毛区稲毛東3丁目)
この地は、1882(明治15)年5月、明治天皇が近衛師団(天皇を守る軍隊)対抗演習をご覧になるため、八街市や千葉市緑区東山科町四谷ヶ原に行幸された時に、休息をとられた所です。碑の近くの案内板には、当時の日程も詳しく紹介されています。
《明治15年の明治天皇行幸》 資料:『タイムトンネル千葉』
・近衛師団の演習の御視察(御統監・天覧)
・5月1日 赤坂の仮皇居を御出発。半蔵門、竹橋、両国橋を経て、伊子田村(現在の小岩?)にて小休止。船橋で昼食、幕張。稲毛で小休止。稲毛から旧穴川十字路を経て椿森を通り千葉神社の脇を抜けて、行在所である千葉町の女子師範学校に御到着。
・5月 2日 女子師範学校から大和橋、病院坂(現在)、船田池の畔を経て現在の大網街道に入り、 仁戸名から当時の誉田村山科抜けて川井村にて小休止。現在の国道126号から野呂村、和泉村を経て八街村丹尾台第一天覧所・大塚山田台第二天覧所。天覧後、中野村の行在所。
・5月3日 中野村から川井村を経て平山村の四谷ヶ原での実設敵対抗演習・混成旅団演習の天覧。平山村での御休憩ののち、千葉町の行在所の女子師範学校に御到着。
・5月 4日 女子師範学校を御出発。稲毛村字カミヤにて小休止、写加村で小休止、そののち、谷津村で小休止、行在所の船橋に御到着。
・5月 5日 船橋の行在所を御出発、市川・小松川・領国を経て、赤坂仮皇居に御到着。- 《参考資料》
- 『稲毛誌』 千葉市立稲毛小学校 (2001) P45~46
- 『皇室がふれた千葉×千葉がふれた皇室』 千葉県文書館 (2015) P74
- 『明治天皇御遺跡』 千葉県教育会(1930)P297~310
- 『千葉県千葉郡誌 [影印版]』『同 復刻版』 千秋社 (1972)(1989) P991~992
- 『タイムトンネル千葉』 千葉市教育委員会 (1995) P251~260
- 『「カルチャー千葉」第38号 (1997)』 千葉市文化振興財団 P35
- 31丹後堰の歴史について知りたい。
-
寒川村の名主の布施丹後は、毎年干ばつに悩まされる周辺農民を救うため、1613(慶長18)年に佐倉藩主の土井利勝の許しを得て、私財を投じて都川の本流、分流の合流地点の星久喜、矢作の境辺に堰を築いて、分流させる土木工事に着手しました。延べ7000人を動員し、丹後堰を完成させました。現在、暗渠に改造されて昔の状態を知ることはできませんが、京葉道路の東側にあるコンクリートの水門より、亥鼻台の北側を通り、お茶の水で南に向かい、南町1丁目で南西に折れて海まで約3.7キロあります。 千葉寺(せんようじ)には、新潼記念塔をはじめ、丹後堰に関する記念碑や多宝塔があり、星久喜町には、丹後堰公園があります。
- 《参考資料》
- 『千葉市誌』 千葉市 (1953) P311~314
- 『千葉市に輝く人びと』 千葉市教育委員会 (1970) P121~129
- 『千葉市史 第2巻 近世近代編』 千葉市(1974)P57~59
- 『写真集 明治大正昭和 千葉』 国書刊行会 (1978)(2020) P100
- 『社寺よりみた千葉の歴史』 千葉市教育委員会 (1984) P142~144
- 『わが町の歴史・千葉』 文一総合出版 (1987) P87~89
- 『千葉いまむかし No.2』千葉市教育委員会(1989) P13~29
- 『丹後堰物語とその補遺』 齋藤 正一郎 (1996)
- 『千葉市の丹後堰と草刈堰の資料』 齋藤 正一郎 (1996)
- 『千葉の歴史夜話』 国書刊行会 (1997) P21~25
- 『遺しておきたい伝えたい千葉の水辺 [その1] (自然・景観・土木遺産)』 ちば河川交流会 (2009) P3~4
- 『わが街の旧跡を訪ねて』 和泉書房 (2009) P38
- 『ちば市史編さん便り』 (ファイル) 千葉市立郷土博物館 (2013) №11
- 『「カルチャー千葉」第7号 (1985)』 千葉市文化振興センター P54~638
- 『「カルチャー千葉」第8号 (1985)』 千葉市文化振興センター P212~229
- 『「カルチャー千葉」第9号 (1986)』 千葉市文化振興センター P152~160
- 『「カルチャー千葉」第10号 (1986)』 千葉市文化振興センター P188~200
- 『「カルチャー千葉」第31号 (1994)』 千葉市文化振興財団 P33
- 30稲毛浅間神社について知りたい。
-
稲毛浅間神社は、大同3(808)年に富士山本宮浅間大社より御神霊を勧請されたと伝えられています。当初は小中台に奉祀された後、現在地の稲毛に移転しました。
主祭神は木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)で、安産子育て・火難除けの守護神として信仰されています。
例年7月15日には、夏の大祭(例大祭)が行われ、子供の健やかな成長を祈って県内をはじめ関東各地からの参拝者で大変賑わいます。
また十二座神楽は、永正元(1504)年に九州方面から移住した神楽の名手が村人に伝授したものと伝えられており、千葉県指定無形文化財に指定されています。- 《参考資料》
- 『稲毛浅間神社』 稲毛浅間神社 (2008)
- 『千葉県神社名鑑』 千葉県神社庁 (1987) P26~P27
- 『社寺よりみた千葉の歴史』 千葉市教育委員会 (1984) P155~P158
- 『千葉市の民俗芸能』 千葉市教育委員会 (1981) P11~P36
- 『千葉市の民話・伝説・歴史ばなし』 千秋社 (1979) P95~P99
- 『稲毛十話』 千葉市立稲毛中学校1年4組 (1990) P41~P46
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』千葉市 (1993) P341~P347
- 『写真集 明治大正昭和 千葉』 国書刊行会 (1978) (2020) P84~P85、P183
- 『目で見る千葉市の100年』 郷土出版社 (2003) P1、P38、P62
- 『写真アルバム 千葉市の昭和』 いき出版 (2011) ⅱ、P28、P123、P173、P202、P235~P236
- 『写真が語る 千葉市の100年』 いき出版 (2021) P58、P185、P265
- 『カメラが撮らえた千葉県の昭和』 中経出版 (2013) P12
- 29千葉駅(JR)の歴史について知りたい。
-
1894(明治27)年7月に総武鉄道(現在の総武本線)が市川~佐倉間に鉄道を 開業し、千葉駅を開設しました。また1896(明治29)年には房総鉄道(現在の外房線)が千葉~大網間に開業しました。
当時の千葉駅は現在の場所から800mほど銚子方面の千葉市民会館周辺にありました。そのため東京方面から房総方面に向かう場合、方向を変える必要があるのでスイッチバックになっていました。
1963(昭和38)年4月に旧千葉機関区にあった現在の場所に駅を移転し、銚子方面と房総方面の線路分岐点を設けてスイッチバックを解消しました。
現在のJR千葉駅は4代目の駅舎です。5つの路線が乗り入れ、千葉都市モノレールや京成電鉄の京成千葉駅と隣接し、千葉県内のターミナル駅の一つになっています。- 《参考資料》
- 『写真集 明治大正昭和 千葉』 国書刊行会 (1978) (2020) P30、P34~P36
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』 (1993) P158~P160、P163~P164
- 『目で見る千葉市の100年』 郷土出版社 (2003) P30~P31、P99、P124~P126
- 『写真アルバム 千葉市の昭和』 いき出版 (2011) ⅵ、P24~P25、P108~P109、P137~P141
- 『千葉の鉄道』 彩流社 (2013) P23~P27
- 『総武線120年の軌跡』JTBパブリッシング (2014) P86~P92
- 『総武線・京葉線』 アルファベータブックス (2015) P52~P55
- 『朝日新聞社機が撮った総武線、京成線の街と駅 1960〜80年代』 フォト・パブリッシング (2017) P64~P67、P93
- 『千葉の鉄道ぶらり途中下車』 フォト・パブリッシング (2018) P43~P45
- 『総武本線、成田線、鹿島線』 フォト・パブリッシング (2020) P54~P63
- 『千葉市市制施行100周年記念誌 百の歴史を千の未来へ』 千葉市市民局 市民自治推進部広報広聴課 (2021) P61
- 『写真が語る 千葉市の100年』 いき出版 (2021) P14、P57、P68~P69、P72、P110、P134、P225~P227、P238~P241
- 『カルチャー千葉 第30号』 千葉市文化振興財団 (1993) P11~P28
- 『地図中心 2019年3月号』 日本地図センター (2019) P12~P15
- 28千葉市の地名の由来について知りたい。
-
千葉市の地名(町名)は、その歴史や地形などに由来するものが多くあります。いくつか下記に事例を挙げます。赤井町...伝承として昔、山の根方から赤い水が湧き出ていたので「赤い泉」、「赤い井戸」、「赤井」と変化して現在の町名になったと伝えられています。要町...町の位置が扇の要のような位置にあるので名付けられたといいます。問屋町...問屋街が形成されており、また将来卸売業者の誘致が計画されていたところから名付けられました。松波...松山つづきの土地の高低から、松の青葉が波の打ち寄せるように見えるところから名付けられたようです。小深町...谷地にある小さな「ふけ田」(足の入るような泥田のこと)が「小ふけ」となって、「小深」の字があてられたといいます。轟町...第二次大戦前、兵器補給廠のあったところで、軍靴の音も賑やかであったところから名付けられたようです。平川町...古くは、千葉氏の家臣、平河氏の所領であったので、村名を平川に改めたと伝えられています。
- 《参考資料》
- 『千葉市の町名 由来・変遷』 千葉市 (1998)
- 『千葉市の町名考』 加曽利貝塚友の会 (1970)
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌(上巻)』 千葉市 (1993)
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌(下巻)』 千葉市 (1993)
- 『日本歴史地名大系 12 千葉県の地名』 平凡社 (1996) P90~P149
- 27千葉市の海岸の変遷(昭和以降)について知りたい。
-
かつて、千葉市内の海岸線は、現在の国道14・16号線付近にありました。遠浅で美しい干潟が広がり、約19キロメートルの海岸線が続いていました。貝や海苔の養殖も盛んに行われ、潮干狩りや海水浴も賑わいました。昭和30年代から本格的に海岸の埋立が始まり、昭和50年代に終了しました。昭和51(1976)年に全長1200メートルの国内初の人工海浜「いなげの浜」が一般公開 されました。その後「検見川の浜」、「幕張の浜」が造成され、合わせて4320メートル の日本一の長さの人工海浜が完成しました。
- 《参考資料》
- 『写真集 千葉市のあゆみ(市勢要覧)2001』千葉市総務局市長公室広報課 第2版
(2001) P30~P31、P74~P77
- 『千葉が誇る日本一 PART1 No.1~No.18』京葉銀行 (2014) No.10
- 『目で見る千葉市の100年』郷土出版社 (2003)
- 『写真アルバム 千葉市の昭和』 いき出版 (2011)
- 『メッセの町は海だった』千秋社(1989)P14~P96
- 『海と緑の街 写真で見る 千葉海浜埋立地の変貌』磯辺街づくり研究会 (2013)
- 『稲毛海浜ニュータウンのあゆみ』 千葉市 (1984) P113~P124
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』千葉市 (1993)
-
「地形図 千葉西部 1:25,000』国土地理院
(1932・1949・1956・1968・1970・1972・1975・1980・1983・1988)
- 『写真集 千葉市のあゆみ(市勢要覧)2001』千葉市総務局市長公室広報課 第2版
- 26高校野球に夏の千葉県大会で戦後の優勝校(甲子園出場校)が、どの高校か知りたい。また、一覧表があれば見たい。
-
全国高等学校野球選手権は、1915(大正4)年の第1回大会から、戦争などの中止をはさみ、2018(平成30)年に第100回を迎えました。『白球を追う 千葉県高校野球データブック』によると、予選地区大会の編成は、1936(昭和11)年~南関東地区大会(神奈川・埼玉・千葉)1948(昭和23)年~南関東大会(埼玉・千葉)1959(昭和34)年~東関東大会(茨城・千葉)1974(昭和49)年~単独予選地区(千葉)になっています。『第100回全国高等学校野球選手権記念東千葉・西千葉大会 熱闘千葉2018』には、「全国大会・関東大会出場校及び春・選手権・秋優勝校」の選手権大会の欄に、1946(昭和21)年から2017(平成29)年までが載っています。また、「全国高等学校野球選手権千葉大会上位進出チーム戦績表」に1948(昭和23)年から2017(平成29)年まで、千葉大会の準々決勝から決勝までのスコアや優勝回数、甲子園試合結果も載っています。『東・西千葉大会展望号 第100回全国高校野球選手権記念』には、「春夏秋の県大会決勝一覧」の各年の夏の欄に、1948(昭和23)年から2017(平成29)年までの優勝校と準優勝校の決勝スコアが載っています。なお、『高校野球グラフ 全国高校野球選手権大会千葉大会』は、1978(昭和53)年から2018 (平成30)年まで所蔵しており(一部欠号あり)、各年の試合結果や選手紹介、新聞記事など、カラー写真が多く掲載されています。
- 《参考資料》
- 『白球を追う 千葉県高校野球データブック』 崙書房/編 (1984) P2、P162~169
- 『第100回全国高等学校野球選手権記念東千葉・西千葉大会 熱闘千葉2018』 千葉県高等学校野球連盟 (2018) P114~120
- 『東・西千葉大会展望号 第100回全国高校野球選手権記念』 ベースボールマガジン社 (2018) P134~135
- 『関東の高校野球 Ⅰ 地域別高校野球シリーズ VOL.16 茨城、千葉』 ベースボールマガジン社 (2014) P74
- 25千葉寺の戻り鐘の伝説について知りたい。
-
『千葉市風土記』によると、次のような伝説とのことです。千葉寺に弘長元(1261)年十二月二十二日の銘が入った梵鐘がありました。改鋳のために江戸に出したところ、ひとりでに「千葉寺・千葉寺」と鳴り出したため、恐ろしがられて再び千葉寺に戻されました。このことから、「戻り鐘」といわれ有名だったということです。戻り鐘の伝説は、明治時代の『千葉誌』や『千葉町案内』、古くは江戸時代の国文学者である高田与清による紀行文『相馬日記』にも記されています。この戻り鐘ですが、『千葉寺いまむかし』に文化年間(1804~1818)になくなってしまったとあります。文化3(1806)年の火災の際になくなった、大巌寺との論争に負けて持ち去られたとの俗説もあるようです。『千葉誌』には割れ鐘のまま鐘楼に掛かっていると書かれており、様々な説が伝わっているようです。現在の鐘は、昭和19(1944)年に軍部の要請で供出した後、昭和32(1957)年に新たに鋳造されたものです。
- 《参考資料》
- 『千葉市風土記』 千葉日報社 (1977) P210
- 『千葉誌』 加藤 久太郎 (1911) P164~165
- 『千葉町案内』 千葉町案内発行所 (1911) P49~50
- 『「相馬日記」『房総文庫 4』影印版』 崙書房(1973)P33
- 『千葉寺いまむかし』 藤澤 妙孝 (2018) P29~30
- 『房総の伝説』 暁書房 (1975) P9
- 『カルチャー千葉 第26号』 千葉市文化振興財団 (1991)P16~17
- 24千葉市が被害を受けた空襲について調べたい
-
千葉市は、1945(昭和20)年6月10日と7月7日に大規模な空襲に遭いました。被害は死傷者1,595人、被災戸数8,904戸、被災者41,212人に及びました。6月10日は日立航空機千葉工場を、7月7日は市街地を標的としたものでした。『考えよう 平和の大切さ』によると轟町・作草部・椿森・弁天地区には軍事関連施設が多く集まっていたことがわかります。『千葉市空襲の記録』によると、6月10日の空襲は、日立航空機千葉工場があった蘇我町と新宿・富士見・新田町・新町付近が被害にあったことがわかります。7月7日の空襲は七夕空襲とも呼ばれており、千葉駅周辺をはじめとする中心市街地と軍事関連施設があった椿森・作草部などにも爆弾が落とされました。さらに、千葉市への空襲は合計10回あったことがわかります。『千葉市史 第2巻 近世近代編』には、空襲の様子が書かれています。『千葉市大空襲とアジア・太平洋戦争の記録』では、100人の方の戦時体験が載っています。その中に、千葉市空襲のことが書かれています。
- 《参考資料》
- 『考えよう 平和の大切さ』 千葉市市民局市民自治推進部市民総務課/編(2017.6)
- 『千葉市空襲の記録』 千葉市空襲を記録する会/編集 (1980.11)
- 『千葉市史 第2巻 近世近代編』 千葉市史編纂委員会/編(1974.3)P482~
- 『千葉市大空襲とアジア・太平洋戦争の記録』 千葉市大空襲とアジア・太平洋戦争の記録100人の証言編集委員会(2009.11)
- 23千葉市の各行政区の名前(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)が決まった経緯を調べたい」
-
千葉市は、1992(平成4)年4月1日に全国で12番目の政令指定都市となりました。政令指定都市へ移行すると同時に6つの区(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)も誕生しました。『政令指定都市へのあゆみ』によると、平成3年9月7日に学識経験者や市民の代表等44名で構成された「千葉市区名選定委員会」が設置されました。10月5日から18日まで名前の募集が行われ、22,910通もの応募がありました。第2回選定委員会で、各区それぞれ5つずつ名前の候補が選定されました。その中には「幕張区」や「亥鼻区」「貝塚区」などの名前もありました。さらに、10月31日に第3回目の選定委員会が開催され、各区の名前が決定しました。選ばれた区名はいずれも公募結果第一位にあったもので、市民の意向が反映される形となりました。『ちば市政だより 平成3年度縮刷版』によると、10月6日発行の市政だより臨時号に区名の募集が載っています。また、11月20日発行の市政だよりによると、10月31日に開催された選定委員会において各区の名前が決定し、千葉市へ答申されたことがわかります。さらに、12月の議会で正式に決定すると書かれています。12月20日発行の市政だよりによると、12月12日に「第4回千葉市議会定例会」が開かれ「千葉市区の設置等に関する条例」が可決されました。これにより、各区の名前が正式決定したことがわかります。また、政令指定都市移行に伴って郵便番号と電話番号も変更になりました。
- 《参考資料》
- 『政令指定都市へのあゆみ』 千葉市企画調整局(1993)132~141ページ
- 『ちば市政だより 縮刷版 15(平成3年度)』 千葉市総務局市長公室(1992.05) 55・66・123・158・181ページ
- 22妙見大祭について
-
千葉市を代表する祭りの一つに「妙見大祭」があります。
『千葉市史 近世近代編』、『千葉市史 現代編』、『社寺からみた千葉の歴史』では、妙見大祭は千葉神社(中央区院内1丁目)でおこなわれている祭礼だとわかります。
千葉神社は、大治元(1126)年、千葉常重が大椎城から猪鼻城に移ったとき、現在の地に祀られたといわれています。明治維新の頃までは北斗山金剛授寺(妙見寺)と言われ妙見尊を祀っていました。妙見尊は、千葉氏の祖先平良文が合戦のとき祈願して、戦に勝ったことから、代々千葉氏の守り神となっていました。神仏分離令が出されると、千葉神社と名称を改めました。また、「妙見尊という神様は我が国にはない」と役人に指摘され、妙見尊と相通じる天地創造の神「天御中主命(あめのみなかぬしのみこと)」を主祭神と定めました。千葉神社の祭礼は大治2(1127)年から始まり、毎年7月16日から22日(明治中期からは新暦の8月16日から22日)までの7日間にわたり、大祭及び神輿御事の神事がおこなわれています。『神輿図鑑4』によると、祭礼の初日、神輿は千葉駅前のメインストリートを通り、千葉県庁そばの香取神社の御旅所(御仮屋)に安置されます。最終日の22日、再び御旅所から担ぎ出された神輿は中央区役所付近の繁華街を通って千葉神社に戻ります。また、寒川神社では毎年8月20日に妙見大祭の祭礼の一部であった「御浜下り」神事がおこなわれています。御浜下りは、神輿が町内を廻った後、海に入り海中を練り歩くというものです。この神事は、当時の寒川村の氏子たちが大漁を祈願して始まったものといわれています。海岸の埋め立てにより一時中断していましたが、平成11(1999)年からポートサイドタワー下の人工海浜で再び行われるようになりました。『房総の神輿』では、妙見大祭が通称「だらだら祭り」と呼ばれていることがわかります。由来は諸説ありますが、祭礼期間が1週間と長いこと、もしくは先触れ太鼓二段打ちの音「だらんだらん」からきていると言われています。- 《参考資料》
- 『千葉市史 第2巻 近世近代編』 千葉市 (1974) p103-107
- 『千葉市史 第3巻 現代編』 千葉市 (1974)p358-360、p452-456
- 『社寺よりみた千葉の歴史』 千葉市教育委員会 (1984) p3-29
- 『神輿図鑑 4』 アクロス (2008) p167-168
- 『房総の神輿』 崙書房出版 (2016) p175-176
- 『カルチャー千葉 第5号』 千葉市文化振興センター (1984) p120
- 『房総の郷土史 9号』 千葉県郷土史研究連絡協議会 (1981) p68-77
- 『星の信仰』渓水社 (1994) p235-264
- 21稲毛区黒砂あたりに川が流れていたのか知りたい
-
現在の稲毛区には排水路のひとつとして、「黒砂水路」があります。
『黒砂いまむかしⅠ 改訂版』によると、かつて黒砂あたりには黒砂浅間神社下から現在の稲毛区役所の裏まで谷津田(谷地にある田んぼ)が広がっていました。京葉工業高校裏にあった溜池から、谷津田に沿って「ひらめ川」という川が黒砂の海まで流れていたことがわかります。『黒砂いまむかし』には、昭和25年頃の黒砂の絵と平成15(2003)年の空中写真が対比されています。「ひらめ川」の自然地形は黒砂村と稲毛村・小中台村の境界となっています。『絵にみる図でよむ千葉市図誌 下巻』の黒砂の地形図や穴川野論絵図(1670年)から、当時の黒砂付近の様子を見ることができます。更に、『千葉市小中台町850番の歴史』にある「小中台町850番地小中台町公営住宅全体配置図」(昭和22年復元図)では当時の様子とともに「ひらめ川」の流れがわかります。
開発が進み、川は昭和47(1972)年に暗渠となり、現在は排水路として掘られた黒砂水路につながっています。『千葉市の水文環境』には「黒砂川」として黒砂水路の概要が紹介されています。- 《参考資料》
- 『黒砂いまむかし Ⅰ 改訂版』 黒砂の資料を保存する会/編(2005) p38-41
- 『黒砂いまむかし』 西田書店黒砂の資料を保存する会/編(2006)
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 下巻』 千葉市史編纂委員会/編(1993)p303-308
- 『千葉市小中台町850番地の歴史』市原 徹/著(2011)
- 『千葉市の水文環境』斎藤 正一郎/[著](1997)
- 20大賀ハスは食べられますか?
-
食用ではありませんが、地下茎を食べることができます。『千葉が誇る日本一 PART1』の「第9回大賀ハス」で、実際にきんぴらになっている大賀ハスの地下茎写真が出ています。こちらの資料によると、味はシャキシャキではなく「粘りがあり、もっちり、ねっとりという食感」とあります。また、大賀ハス自体を食する訳ではありませんが、蓮の葉にお酒など注ぎ入れ葉茎を使って飲む「象鼻杯」が千葉市千葉公園の「大賀蓮を観る会」で行われています。「象鼻杯」は古代中国が始まりではないかとされ、『蓮への招待』によると「茎の中を酒が通る間に、微かな蓮の香りが酒に伝わり清涼感が味わえる」そうです。
- 《参考資料》
- 『千葉が誇る日本一 PART1』 京葉銀行(2014)第9回大賀ハス
- 『蓮への招待』 西田書店(2004)p380-383
- 『蓮 ハスをたのしむ』 ネット武蔵野(2000)p16-17
- 『レンコン<ハス>の絵本』 農山漁村文化協会(2008)
《参考ホームページ》
【千葉市ホームページ/千葉市千葉公園ホームページ】
http://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/chuo-inage/chibakouen.html
- 19千葉常胤(つねたね)について知りたい。
-
千葉常胤(元永元(1118)年~建仁元(1201)年)は、源頼朝から「今日よりは御身を父と仰ぐべし」と厚い信頼を寄せられた人物です。千葉氏は、平安時代末期から戦国時代末期まで約470年にわたり下総国を中心とした地域を治め、特に、頼朝に仕えた常胤の活躍が下総千葉氏の発展のもととなったと言われています。
『[千葉市立郷土博物館]研究紀要 第7号』から常胤と頼朝の関係や常胤の動向がわかります。治承4(1180)年、源頼朝が石橋山の戦いに敗れて安房に逃れてきた際に、常胤は一早く頼朝の元に参上し、その再起に大きく貢献しました。後には上総・下総をはじめ奥州、東海、九州にまで及ぶ広大な所領を獲得し、幕府屈指の御家人に成長しました。やがてそれらの領地を6人の子どもたちに継がせ、千葉氏の基礎を固いものにしました。
『千葉県の歴史 史跡と人物でつづる』からは、千葉県の歴史を通した常胤の活躍の様子がわかり、『千葉の先人たち』には常胤の生い立ちがわかりやすくまとめられています。また、『源頼朝・義経と千葉介常胤』には、常胤の坐像や武具等関連資料が紹介されています。 千葉氏についての資料や千葉市内の文化財、市の歴史等に関連する資料は、千葉市立郷土博物館で見ることができます。- 《参考資料》
- 『[千葉市立郷土博物館]研究紀要 第7号』 千葉市立郷土博物館 (2001)
- 『千葉県の歴史 史跡と人物でつづる 改訂版』 光文書院 (1986)p57-65
- 『千葉の先人たち』 光文書院 (1981)p8-19
- 『源頼朝・義経と千葉介常胤』 千葉市立郷土博物館 (2005)
- 『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』 千葉市 (1974)
- 『千葉常胤 新装版』 吉川弘文館 (1987)
- 『千葉大系図 全 附 千葉家世紀』 千葉開府八百年記念祭協賛会(1926)
- 『まんが千葉県の歴史 2 平安時代~鎌倉時代』 日本標準(2001)
- 『おはなし千葉の歴史』 岩崎書店(2012)p23-25
- 『伸びゆく千葉市 [令和3年]』 千葉市教育委員会 (2021)p48-49
- 『千葉常胤公ものがたり』 千葉市(2016)
- 『千葉一族入門事典』 啓文社書房(2016)
- 『4つのたからもの』 千葉日報社(2018)P13-16
- 『千葉常胤と鎌倉幕府の成立』 千葉市立郷土博物館(2018)
- 『千葉常胤とその子どもたち』 啓文社書房(2018)
- 『千葉氏入門 Q&A』 千葉市立郷土博物館 (2019)
- 『千葉一族の歴史』 戎光祥出版(2021)
- 『千葉市市制施行100周年記念誌 百の歴史を千の未来へ』 千葉市(2021)P26-27
- 『千葉常胤と13人の御家人たち 南関東編』 千葉市立郷土博物館(2022)
- 『史料で学ぶ千葉市の今むかし』 千葉市(2022)P56-65
《参考ホームページ》
【千葉市ホームページ/千葉市立郷土博物館ホームページ】
https://www.city.chiba.jp/kyodo/
- 18稲毛にあった「海気館」にどんな人が泊ったのか知りたい。
-
「海気館」は、海水浴や海辺の空気が健康によいという考えから、医師の浜野昇によって明治21(1888)年に「稲毛海気療養所」として現在の千葉市稲毛区に設置されました。『千葉いまむかしNo.23』によると、肺病、貧血症、重病後の快復期、転地療養を必要とする人など、いろいろな症状に効果があると新聞広告でうたっています。当時はこのような病人や健康志向の人々が訪れていたようです。しかし開所後間もなく千葉市中央区にあった加納屋旅館に営業が移り、明治24(1891)年に刊行された『千葉繁昌記』では「加納屋支店海気館」として紹介されています。明治29(1896)年には当時官僚だった原敬(のちの第19代内閣総理大臣)が保養のため、旅館「海気館」に宿泊しています。また、明治の終わり頃に森鷗外、島崎藤村、田山花袋、昭和9年には林芙美子などといった文人墨客も訪れており、田山花袋の『弟』、林芙美子の『追憶』といった「海気館」の登場する作品も書かれています。現在、「海気館」は取り壊されすでにありませんが、『江戸東京湾事典』に新しい経営者が「全面的に改修して、1965年初めまで旅館を経営した」とあり、戦後まで多くの人に利用されていたようです。
- 《参考資料》
- 『千葉いまむかしNo.23』 千葉市教育委員会(2010) P.11-24
- 『千葉繁昌記』 千葉市教育委員会(1964)(1891年の復刻版) P.43-45
- 『千葉県の歴史 資料編 近現代7』 千葉県(1998)
- 『千葉町の発展と海水浴場』 千葉市みどりの協会(2009)
- 『文学の旅・千葉県』 滝書房(2003)
- 『文人ゆかりの地 ちばカレッジ記録集 平成16年度』 千葉市生涯学習センター(2005) P.16-17
- 『原敬日記 2-1』 乾元社(1950) P.196-197
- 『東京湾岸地区集 1』(田山花袋『弟』/林芙美子『追憶』を収録) あさひふれんど千葉(1995)
- 『江戸東京湾事典』新人物往来社(1991) P.312-313
- 17最近千葉市に引っ越してきたのですが、自分の住む区のことを知りたいです。何か便利な資料はありますか。
-
各区ごとに分かれて紹介されている資料の一つとして、『区ガイド』があります。折りたたみ式で、施設の案内や問い合わせ先等があり、裏面はガイドマップになっています。お住まいの区の周辺を実際に散策するなら、『健康づくり支援マップ[区版]』があります。各区のウォーキングコースが距離や時間等とともに紹介されています。また、健康課のご案内など、健康に関する情報があります。千葉市について知るためには『千葉市勢要覧 2011』から千葉市や各区の概要がわかります。また、散策のガイドにするなら、『今週末、千葉の緑に会いたくなる本』(『今週末、千葉の海に会いたくなる本』)や『るるぶ千葉6区』等に各地域のおすすめ情報等が紹介されています。千葉市の歴史を知るには、『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻・下巻』や『千葉市の町名 [1993]』から町の成り立ち等がわかります。更に各地域の歴史としては、『メッセの町は海だった』や『海と緑の街』、『おゆみ野風土記』等から当時の様子を伺うことができます。
- 《参考資料》
- 『[千葉市] 区ガイド』千葉市 (2009-)
- 『健康づくり支援マップ[区版]』 千葉市保健福祉局健康部健康支援課 (2008-)
- 『千葉市自転車走りやすさマップ』 千葉市建設局土木部自転車対策課 (2013)
- 『千葉市勢要覧 2011 市制施行90周年記念』千葉市総合政策局市民自治推進部広報課 (2011)
- 『今週末、千葉の緑に会いたくなる本 千葉市観光ガイドブック "umidori"』 千葉市 (2014)
- 『るるぶ千葉6区』 JTBパブリッシング (2006)
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻・下巻』 千葉市 (1993)
- 『千葉市の町名 [1993]・[1998]』 千葉市市民生活局市民部区政課 (1993・1998)
- 『メッセの町は海だった』 千秋社 (1989)
- 『海と緑の街』 磯辺街づくり研究会 (2013)
- 『稲毛十話』 千葉市立稲毛中学校1年4組 (1990)
- 『おゆみ野風土記』 おゆみ野の昔を知る会実行委員事務局 (2004)
- 『都川通信』各号 齋藤 正一郎 (1991-2001)
- 『けみがわ』 検見川小学校同窓会 (1992)
- 『千葉しらい風土記』 千葉白井風土記編纂会 (2011)
- 『さらしな風土記』 更科郷土史研究会 (1999)
- 『さらしな風土記 史料編(第1集)』 更科郷土史研究会 (2000)
- 『タイムスリップちば』 地域の歴史文化勉強会 (2018)
- 『わたしたちのまち』 花見川地元を学ぶ会 (2021)
≪参考ホームページ≫
【千葉市ホームページ/健康支援課 ・健康づくり支援マップ】
https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/kenkofukushi/suishin/kenkoudukurisienmappu.html
- 16加曽利貝塚(千葉市若葉区桜木町)について知りたい。
-
『加曽利貝塚』には、環状形をした縄文時代中期の「北貝塚」と、馬蹄形をした縄文時代後期の南貝塚が連結して、特殊な「8の字」形をした国内最大級の縄文貝塚です。北貝塚は、縄文中期から後期前半にかけて、南貝塚は縄文後期から晩期にかけて形成されたもので、北貝塚は昭和46(1971)年、南貝塚は昭和52(1977)年にそれぞれ国の史跡に指定されています。また、平成29(2017)年10月、国の「特別史跡」に指定されました。貝塚の調査活動やその歴史などについては『史跡 加曽利貝塚 総括報告書第1分冊』、人骨や縄文式土器、堅穴式住居跡などの出土物については、『史跡 加曽利貝塚 総括報告書 第2分冊』、発掘の成果と考察については、『史跡 加曽利貝塚 総括報告書第3分冊』から知ることができます。
また、昭和41(1966)年に開館した史跡公園の千葉市立加曽利貝塚博物館では、実際に発掘された貝層断面と堅穴住居跡群を見学することができます。- 《参考資料》
- 『加曽利貝塚 東京湾東岸の大型環状貝塚 日本の遺跡46』 同成社(2013)
- 『貝塚博物館紀要 創刊号~』 千葉市立加曽利貝塚博物館(1968~)
- 『加曽利貝塚』 千葉市立加曽利貝塚博物館(1999)
- 『加曽利貝塚 1 貝塚博物館調査資料 1』 千葉市加曽利貝塚博物館(1968)
- 『加曽利貝塚 2 貝塚博物館調査資料 2』 千葉市加曽利貝塚博物館(1968)
- 『貝塚博物館研究資料 第5集』 千葉市立加曽利貝塚博物館(1999)
- 『千葉市史 第1巻 原始古代中世編』 千葉市(1974)
- 『千葉市史 史料編 1 原始古代中世』 千葉市(1976)
- 『縄文時代 1 房総考古学ライブラリー 2』 千葉県文化財センター (1985)
- 『史跡 加曽利貝塚 総括報告書 第1分冊~第3分冊』 千葉市教育委員会(2017)
- 『史跡 加曽利貝塚保存活用計画書』 千葉市教育委員会(2017)
- 『加曽利貝塚博物館 特別史跡 加曽利貝塚』 加曽利貝塚博物館(2020)
《参考ホームページ》
【千葉市立加曽利貝塚博物館】
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/shogaigakushu/shogaigakushu/kasorikaizuka/top.html
【千葉市埋蔵文化財調査センター】
https://www.city.chiba.jp/shisetsu/bunka/0017.html
- 15 こじま公園(美浜区高洲)にあった海洋公民館について知りたい。
-
海洋公民館は、全国的に船を利用した珍しい施設として、昭和41 (1966)年5月に開館しました。『稲毛海浜ニュータウンのあゆみ』によると、「昭和40年4月に廃船となった海上保安大学の練習船「こじま」を千葉市が払い下げを受け、改装して海洋公民館として利用した」とあり、展示や施設の設備等についても紹介されています。施設として利用された「こじま」の経歴については、『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』に、「「こじま」は1945 (昭和20)年3月、佐世保で旧海軍の海防艦「志賀」として竣工した」とあり、戦艦として使用されていたと記述されています。更に、戦後、米軍連絡船や中央気象台定点観測船として就航するなど、戦後の活躍などがわかります。また、『ざ・京葉ベイエリア その変貌録』には、「こじま」の写真等が掲載されています。海洋公民館は、老朽化などのため平成5 (1993)年に閉館し、平成10 (1998)年3月に「こじま」は解体されました。現在、解体されたこじまの一部が稲毛記念館 (美浜区高浜) に展示されています。《参考資料》
- 『稲毛海浜ニュータウンのあゆみ』 千葉市 (1984) p73
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』 千葉市 (1993) p604
- 『ざ・京葉ベイエリア その変貌録』 サン・スキラ出版 (2004) p64-65
- 『千葉市のしおり』 千葉市役所 (1967) p22
- 『千葉市史 第3巻 (現代編)』 千葉市 (1974) p354-355
- 『ニューライフちば №400』 千葉県広報協会 (1996) p24-25
- 14 矢作トンネルの上にある高架水槽について知りたい。
- 千葉高架水槽(千葉市中央区矢作町)は、12角形で高さ30メートル、昭和12(1937)年に完成した県営上水道事業草創期の施設です。
『千葉県の産業・交通遺跡』には、「旧千葉県都川給水塔」として、鉄筋コンクリート造5階建の高架水槽の4・5階に水槽があり、水圧の足りない標高の高いところへの配水のための施設とあります。
『千葉県営水道史』には、県営水道発足時の詳しい状況と、創設から45年間の水道局の変遷についてまとめられています。さらに、平成15(2003)年度に社団法人 土木学会の選奨土木遺産として認定され、平成19(2007)年7月31日には国の登録有形文化財(建造物)としても登録されています。
千葉県水道局のホームページには、認定・登録についての詳しい説明があり、毎年桜の季節に、見学会が行われています。
- 《参考資料》
- 『千葉県営水道史』 千葉県水道局(1982)
- 『千葉県の産業・交通遺跡』 千葉県教育委員会 (1998)
- 『千葉県土木史』 千葉県県土整備部(2007)
- 『遺しておきたい伝えたい千葉の水辺 その1』 ちば河川交流会(2009)
- 『遺しておきたい伝えたい千葉の水辺 その3』 ちば河川交流会(2011)
- 『日本の土木遺産』 講談社(2012)
《参考ホームページ》【千葉県ホームページ/水道局・文化遺産に認定等された水道施設】
- 13 千葉市の人口が知りたい。
-
千葉市の人口は、『千葉市統計書』で調べることができます。『千葉市統計書』は毎年刊行されており、千葉市の人口をはじめとする様々な統計データを確認することが出来ます。最新の人口は「ちば市政だより」(毎月1発行)で確認することができます。また、千葉市ホームページでは『町丁別人口別及び世帯数』には1カ月前の、『年齢別人口』及び『町丁別年齢別人口』には各区の3カ月前の人口が掲載されております。
《参考資料》
- 『千葉市統計書』 千葉市政策企画課(1968-)
- 『千葉市の推計人口』 千葉市政策企画課統計室 (1993-)
- 『数字上より見たる千葉市の変遷 千葉開府八百年記念』 千葉市役所(1926)
- 『千葉いまむかし No.5』 千葉市教育委員会(1992)
- 『千葉県統計年鑑』 千葉県統計課(1957-)
《参考ホームページ》【千葉市ホームページ/政策企画課統計室 トップページ】【千葉県ホームページ/統計情報の広場(千葉県の統計情報)】【町丁別人口別及び世帯数】【町丁別年齢別人口】
- 12 大賀ハスを発見したときの資料を探しています。
-
大賀ハスは、千葉市の花として親しまれています。
千葉市郷土博物館発行の『大賀ハス』には、昭和26(1951)年3月30日、大賀一郎博士の推論のもと、現検見川東大総合運動場の地下5mの青泥層から発掘された3粒の古蓮の実のうち1粒が発芽し、翌27(1952)年7月18日に開花したことや、2000年以上もの眠りから蘇った古代蓮が、世界最古の花として米国ライフ誌にも紹介され、世界的な反響を呼んだこと等が記され、p25の「大賀ハスの分根先一覧」から、日本のみならず世界各国へも分根されたことがわかります。
また、博士は、著書である、『ハス』や『大賀一郎 ハスと共に六十年』で、発掘に至るまでの経緯などを詳細に記しています。特に『大賀一郎 ハスと共に六十年』には、千葉市立花園中学校で開催された大賀ハス発掘碑完成記念講演が掲載されており、大賀ハスの発掘について、エピソードも踏まえて語られています。『二千年の眠りから覚めて 大賀ハス開花五十周年記念誌』のp16には「花園地区と大賀ハスの年表」や、大賀博士の「大賀ハス発掘碑」除幕式での感謝のことばが掲載されています。
なお、大賀ハスは昭和29(1954)年3月31日に千葉県の天然記念物に、平成5(1993)年4月29日に市の花と制定されています。
《参考資料》
- 『大賀ハス』 千葉市立郷土博物館 (1988)
- 『二千年の眠りから覚めて 大賀ハス開花五十周年記念誌』 花園ハス祭り実行委員会 (2001)
- 『ハス』 内田老鶴圃 (1960) (『ハスを語る』 (忍書院 1954年刊)の改題))
- 『大賀一郎 ハスと共に六十年』 日本図書センター (1999) (『ハスと共に六十年』(アポロン社 1965年刊)の改題)
- 『まぼろしの花がさいた―二千年まえのハスを開花させた大賀一郎博士の六十年』 くもん出版 (1988)
- 『ここを掘ればハスの実が出る―大賀ハス由来』 鷗友学園生物教室 (1970)
- 『千葉が誇る日本一 PART1』 京葉銀行 (2014) №9
- 『4つのたからもの』 千葉日報社 (2018) P9-12
- 『百の歴史を千の未来へ 千葉市制100周年記念漫画』 千葉市 (2021) P111-132
- 『千葉市オーラルヒストリー 大賀ハス 伊原茂久氏インタビュー編』 千葉市中央図書館 (2021)
- 『千葉市オーラルヒストリー 大賀ハス 南定雄氏インタビュー編』 千葉市中央図書館 (2021)
- 『史料で学ぶ千葉市の今むかし』 千葉市 (2022) P16-17
- 『大賀ハス開花70周年記念誌』 大賀ハス開花70周年記念事業実行員会 (2023)
《参考ホームページ》【千葉市ホームページ/千葉市のプロフィール>市の花オオガハス】http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kohokocho/prfindex.html#hana
【千葉県ホームページ/千葉市の国・県指定および国登録文化財>千葉市の記念物>検見川の大賀蓮】
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai/p431-033.html
【大賀ハス何でも情報館】
https://www.city.chiba.jp/toshi/koenryokuchi/kanri/chuo-mihama/chibap06ogahasu.html
- 11 江戸時代、印旛沼の水を、花見川から東京湾へ流す掘割工事があったというが、どのような工事だったのか。
-
『印旛沼開発史』をはじめ、『千葉市史 第2巻(近世近代編)』や、『人づくり風土記12千葉』等に、「印旛沼の堀割工事は、享保、天明、天保と江戸時代に3回にわたって行われたが、いずれも途中で中止され失敗に終わった」ことが記されています。
なかでも天保の工事は、幕府が沼津藩をはじめ担当区を五つの藩に分けて行わせた工事で、『千葉市史 第2巻(近世近代編)』や『千葉いまむかしNo.4』に、鳥取藩に割り当てられた区(柏井村~天戸村)が、花島村地内の泥土層のため難工事になったことが記載されています。 なお、『千葉いまむかし』の『No.4』、『No.6』、『No.10』には、鳥取藩・庄内藩・沼津藩・秋月藩の天保期の工事についての論文が収録されています(下記参考資料参照)。
この工事は、明治以降も試みられ、『人づくり風土記12 千葉』には、「昭和40年代に完成し、東京湾に1本の川として流れるようになり、上流を新川(八千代市)、下流を花見川と呼んでいる」という記述があります。《参考資料》
- 『印旛沼開発史 第1部 [上巻]』 印旛沼開発史刊行会 (1972)
- 『千葉市史 第2巻(近世近代編)』 千葉市(1974)p63-66
- 『人づくり風土記12千葉』 農山漁村文化協会(1990)p66-73
- 『千葉いまむかし No.4』(鳥取藩・庄内藩) 千葉市教育委員会(1991)p19-69
- 『千葉いまむかし No.6』(沼津藩・秋月藩) 千葉市教育委員会(1993)p31-71
- 『千葉いまむかし No.10』(秋月藩) 千葉市教育委員会(1997)p113-162
- 『千葉いまむかし No.11』 千葉市教育委員会(1998)p69-120
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 下巻』 千葉市(1993)p460-464
- 『千葉の歴史夜話』 国書刊行会(1997)p15-21
- 『図説千葉県の歴史』 河出書房新社(1989)p190-194
- 『天保期の印旛沼堀割普請』 千葉市(1998)
- 『天保改革と印旛沼普請』 同成社(2001)
- 『明治期の印旛沼開疏計画―研究資料抄録―』 杉浦淳三(2006)
- 『千葉市の河川 平成2年度』 千葉市建設局土木部河川課(1990)p14-15
- 10 都川について調べたい。
-
千葉県千葉土木事務所が発行した『都川』に、都川水系とその流域が、地形図とともに記載されています。また、この資料には、明治14(1881)年頃と大正10(1921)年頃の都川沿川地域の様子が地形図、写真を添えて紹介されており、都川の変遷を知ることができます。
都川の歴史と、流域に住んだ人々との歴史と文化についての研究は、『改稿 都川物語(都川通信No.114)』をはじめとした『都川通信』各号で齋藤正一郎氏により詳しく述べられています。また、都川流域の自然を調べるなら『行こうさぐろう緑と水辺』や『千葉県の自然誌』、水質調査については『千葉市環境白書』等に記載があります。さらに『エコライフちば』等では環境団体による都川をきれいにするための活動が紹介されています。《参考資料》
- 『千葉大百科事典』 千葉日報社 (1982) p904
- 『千葉市史 第1巻 (原始古代中世編)』 千葉市 (1974) p14ほか
- 『都川』 千葉県千葉土木事務所 (2001)
- 『都川観察ノート』 千葉県千葉土木事務所 (2001)
- 『都川通信』各号 齋藤 正一郎 (1991-2001)
- 『行こうさぐろう緑と水辺』 千葉市 (1988) p36-51
- 『千葉県の自然誌 本編6 千葉県の動物1 -陸と淡水の動物-』 千葉県 (2002) p50-61
- 『千葉県の自然誌 別編2 千葉県植物写真集』 千葉県 (2005) p243
- 『カルチャー千葉 第31号』 千葉市文化振興財団 (1994) p36-41
- 『都川をあるく』 中居 賢一 (1991)
- 『都川の歴史を訪ねて』 千葉の歴史を知る会 (1975)
- 『千葉市環境白書』 千葉市環境局環境保全部 (1977-)
- 『エコライフちば』各号 千葉市環境保全課 (1995-2015)
- 『企画情報 No.12』 千葉市企画課 (1991) p77-83
- 『わたしたちの千葉市 平成10年度版』 千葉市教育委員会 (1998) p11-14
- 『千葉市の川にすむいきものたち』 千葉市環境保全課 (2011) p4
《参考ホームページ》【千葉市ホームページ/都川水の里公園のホームページ】
- 9 千葉市にあった城などについて調べたい
-
城郭の歴史については、『日本城郭大系6 千葉・神奈川』に築城者や築城年、場所や由来などの詳しい記述があり、多くの城跡が紹介されています。『千葉県の歴史 資料編 中世1』では、主だった城跡の場所や由来、実際の出土物や遺構の様子などが写真付きで詳しく紹介されています。『房総の古城址めぐり上巻・下巻』は、上巻に安房上総(千葉市北西部あたり)が、下巻には下総国(千葉市南部あたり)の城跡が紹介されています。これら3誌は千葉市以外の城跡についても紹介されています。
実際の出土物や遺構については、『千葉市猪鼻城跡』『千葉市生実城』などの個々の遺跡の発掘報告書に発掘の経緯とともに詳しく紹介されています。
また、『絵にみる図でよむ千葉市図誌上巻・下巻』では、城跡についての記述は多くはありませんが、掲載されている古地図の中で、城跡の位置を確認することができるものもあります。《参考資料》
- 『日本城郭大系6 千葉・神奈川』 新人物往来社 (1980)
- 『千葉県の歴史 資料編 中世1』 千葉県 (1998)
- 『図説房総の城郭 改訂版』 国書刊行会 (2006)
- 『房総の古城址めぐり 上巻』 有峰書店新社 (1977)
- 『房総の古城址めぐり 下巻』 有峰書店新社 (1982)
- 『千葉市猪鼻城跡』 千葉市文化財調査協会 (1999)
- 『千葉市生実城跡』 千葉市文化財調査協会 (2001)
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』 千葉市 (1993)
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 下巻』 千葉市 (1993)
- 『千葉いまむかし №8』 千葉市教育委員会 (1995)p39-56
- 『千葉いまむかし №11』 千葉市教育委員会 (1998)p1-32
- 『千葉いまむかし №13』 千葉市教育委員会 (2000)
- 『千葉いまむかし №18』 千葉市教育委員会 (2005)p41-60
- 『千葉城郭研究 第1号~第10号~』 千葉市城郭研究会 (1989-2011)
- 8 「絶滅危惧種」について調べたい。特に千葉県内の絶滅危惧種に関する資料はありますか。
-
絶滅危惧種とは環境変化や乱獲などが原因で、すでに絶滅した、または絶滅寸前になっている動物や植物の種のことをいい、環境省ではレッドリスト(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種のリスト)を作成・公表するとともに、これを基にした レッドデータブック(日本の絶滅のおそれのある野生生物の種について、それらの生息状況等を取りまとめたもの)を刊行しています。
国内のレッドデータブックやリストは都道府県等の団体でも作成しており、千葉県、千葉市からも下記のような資料が刊行されています。
なお、千葉県レッドデータブック・レッドリストは、千葉県環境生活部自然保護課自然環境規格室の生物多様性センターホームページにある「絶滅危惧種の保護」から、また千葉市レッドリストは、千葉市環境保全部ホームページからダウンロードすることができます。《参考資料》
- 『千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドデータブック‐普及版‐』 千葉県環境生活部自然保護課 (2001)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドデータブック‐動物編‐』 千葉県環境部自然保護課 (2000)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドデータブック‐植物編‐』 千葉県環境部自然保護課(1999)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドリスト(植物編)維管束植物 改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2003)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドリスト(植物編)2004年改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2004)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物―千葉県レッドリスト(動物編)2006年改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2006)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドデータブック 植物・菌類編 2009年改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2009)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドデータブック 動物編 2011年改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2011)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドリスト 植物・菌類編 2017年改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2017)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドリスト 動物編 2019年改訂版』 千葉県環境生活部自然保護課(2019)
- 『千葉県の保護上重要な野生生物 千葉県レッドデータブック 群衆・群落編』 千葉県環境生活部自然保護課(2020)
- 『千葉県の自然誌 別編2 千葉県植物写真集 』 千葉県 (2005) p326-385
- 『千葉市の保護上重要な野生生物―千葉市レッドリスト―』 千葉市環境保全推進課(2004)
《参考ホームページ》【千葉県ホームページ/生物多様性センター(千葉県立中央博物館内)】【千葉市の保護上重要な野生生物-千葉市レッドリスト-】
- 7 子どものころ(戦前)に稲毛あたりの海岸で潮干狩りをした記憶があるが、その頃の稲毛海岸の写真などが紹介されている本がみたい。
-
『市民フォトちば 2003 秋号』に「かつての海の保養地 稲毛の歴史を探る」が特集されており、戦前の稲毛 海岸の風景や潮干狩りの写真が掲載されています。『海と緑の街 写真で見る 千葉海浜埋立地の変貌/稿本』では稲毛海岸の風景を写した大正期~昭和初期の絵葉書が紹介されています。
また、稲毛海岸以外では、『メッセの町は海だった 』や『千葉市制施行70周年』、『写真集 明治大正昭和 千葉』に、幕張や出洲海岸の戦前の海岸風景の写真が掲載されています。《参考資料》
- 『市民フォトちば 2003 秋号』 千葉市広報課(2003) P4-5
-
『海と緑の街 写真で見る 千葉海浜埋立地の変貌/稿本』 磯辺街づくり研究会(2013)
- 『メッセの町は海だった』 千秋社(1989)p42-43
- 『千葉市制施行70周年』 千葉市広報課(1991)p54
- 『写真集 明治大正昭和 千葉』 国書刊行会(1978)(2020) P110-117
- 『写真集 千葉市のあゆみ 第2版』 千葉市(2001)p30-31
-
『加藤博仁氏絵葉書コレクション 旅してみよう千葉のむかし』 千葉市立郷土博物館 (2011) p5-6
-
『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』 千葉市(1993) P600
-
『目で見る千葉市の100年』 郷土出版社(2003)P38
-
『海と千葉』 千葉市立郷土博物館(2020)P30-34 P38-39
-
『千葉市市制施行100周年記念誌』 千葉市広報広聴課(2021)P38-39 P54
- 6 御成街道について調べたい。
-
『東金御成街道を探る』では、御成街道は、「(徳川)家康の東金辺での鷹狩りが計画され、急遽、沿道の村々の農民を総動員して短期間で造り上げた道」であり、「船橋から東金まで約37kmにわたり、ほぼ直線で結ばれ」ていると解説されています(p1)。
『房総の道 東金御成街道』のp24-26には、「この道の造成に当っては、所々にあった大木に昼は白旗を、夜は提灯を掲げて突貫工事をしたとか、一夜で完成したとか、「三日三晩」で造成したという伝承が残っており、別名を「提灯街道」、「一夜街道」「権現道」とも呼ばれている」という記述があります。
また、『カルチャー千葉 第46号』p26のコラム「千葉市地名辞典」で、御成台や御殿町など、この御成街道にちなんだ地名が紹介されています。
また、この街道沿いには、家康の休憩・宿泊施設も建設されました。その一つに御茶屋御殿(おちゃやごてん) の遺跡があり、その様子は『お成り街道 家康鷹狩り道』や、『千葉市の散歩道』等に紹介されています。《参考資料》
- 『東金御成街道を探る』 暁印書館(1998)
- 『房総の歴史街道絵本』 崙書房出版(2002)p9-18
- 『東金御成街道史跡散歩』 暁印書館(2000)
- 『房総の道 東金御成街道』 聚海書林(1991)
- 『お成り街道』 本保弘文(1986)
- 『千葉市歴史散歩』 千葉市教育委員会文化課(1994)p54-
- 『市民フォトちば 2002年秋号』 千葉市 (2002) 特集:御成街道と御茶屋御殿 p3-12
- 『カルチャーちば 第28号』千葉市文化振興財団(1992)特集:謎の御成街道を行く p11-34
- 『カルチャーちば 第38号』千葉市文化振興財団(1997)特集:千葉を旅する,千葉から旅する p26-29
- 『カルチャーちば 第46号』千葉市文化振興財団(2005)特集:千葉の古道を歩く p23-25
- 『千葉市の散歩道』 千葉市(2010)
- 5 千葉市の社寺、仏像について調べたい。
-
『社寺よりみた千葉の歴史』には、千葉神社を始め、千葉市内の神社・寺・仏像に関する記述があります。またそれにまつわる歴史についても述べられています。
千葉市内仏像彫刻所在調査報告』は、昭和63(1988)年度からの3年間に市が行った仏像彫刻所在調査の記録をまとめたものです。この調査を踏まえて編纂された『千葉市の仏像』には、千葉市内に所在する仏像彫刻のうち、歴史・文化及び美術的見地から重要と判断されたものについての写真図版や、詳細な解説が記載されています。
また、『全国寺院名鑑 千葉県版』では、県内の寺院名簿と著名寺院の本尊、由緒等が、『千葉県神社名鑑』では県内の神社とその祭神、由緒等がまとめられています。
その他、市内各地の石造文化財についての資料には『千葉市文化財調査報告書 第5集 路傍の石仏』があります。『千葉市史』、『千葉市風土記』にも千葉の社寺・仏像についての記述が含まれています。
千葉市美術館で行われた、千葉県内の様々な時代の仏像を集めた展示会の図録、『房総の神と仏』と『仏像半島 房総の美しき仏たち』では、カラー写真でそれぞれの仏像が紹介されています。《参考資料》
- 『社寺よりみた千葉の歴史』 千葉市教育委員会 (1984)
- 『全国寺院名鑑 千葉県版』 寺院名鑑刊行会事務局 (1970)
- 『千葉県神社名鑑』 千葉県神社庁 (1987)
- 『房総の古社』 有峰書店新社 (1985)
- 『千葉市内仏像彫刻所在調査報告』 千葉市教育委員会 (1991)
- 『千葉市の仏像』 千葉市教育委員会 (1992)
- 『千葉市文化財調査報告書 第5集 路傍の石仏』 千葉市教育委員会 (1981)
- 『千葉市史』 千葉市 (1974-2021)
- 『千葉市風土記』 千葉日報社 (1981改訂)
- 『房総の神と仏』 千葉市美術館 (1999)
- 『仏像半島 房総の美しき仏たち』 千葉市美術館 (2013)
- 4 千葉を襲った地震・台風など自然災害について知りたい
-
『千葉県の自然誌 本編2 千葉県の大地』のほか、『検証・房総の地震』や『地震と房総』には、過去に発生した地震の記録や、千葉県を襲う地震のメカニズムについて述べられています。
また、千葉県における台風災害については、『千葉県の自然誌 本編3千葉県の気候・気象』に記述があります。
より古い時代のことについて知りたい時は『千葉県気象災害史』を見ると日本書紀、江戸時代の日記等の古文書や、千葉県史などにみられる千葉県内の自然災害に関する記述が昭和30年代まで抽出されています。
『千葉県気象災害史(第2集)』は、昭和44(1969)年~昭和60(1985) 年までの千葉県に関する自然災害について述べられています。
また、令和元年9月5日に南鳥島近海で発生した台風15号は、過去69年間で関東地方に上陸した台風としては最強クラスの勢力で、9日、千葉県を中心に甚大な被害をもたらしました。その様子は 『令和元年房総半島台風等への対応に関する検証報告書』などから窺い知ることができます。《参考資料》
- 『千葉県の自然誌 本編2』 千葉県 (1997)
- 『検証・房総の地震』 千葉日報社 (1997)
- 『地震と房総』 千葉県立中央博物館 (1990)
- 『千葉県の自然誌 本編3』 千葉県 (1999)
- 『千葉県気象災害史』 千葉県気象災害連絡協議会(1956)
- 『千葉県気象災害史(第2集)』 日本気象協会(1987)
- 『房総災害史』 千秋社(1984)
- 『防災誌 元禄地震 第2改訂版』 千葉県総務部消防地震防災課(2009)
- 『防災誌 関東大震災』 千葉県総務部消防地震防災課(2009)
- 『防災誌 風水害との闘い』 千葉県総務部消防地震防災課(2010)
- 『房総沖巨大地震』 崙書房 (1983)
- 『安房震災誌 復刻版』 臨川書店 (1987)
- 『令和元年房総半島台風等への対応に関する検証報告書』 千葉県 (2020)
- 『令和元年房総半島台風等への対応に関する検証報告書 概要』 千葉県 (2020)
- 『令和元年房総半島台風等への対応に関する検証 (関連資料1) 』 千葉県 (2020)
- 『令和元年房総半島台風等への対応に関する検証 (関連資料2)』 千葉県 (2020)
- 『令和元年災害記録誌』 千葉市総務局危機管理課 (2020)
- 『倒木が語るあの日』 富津のまちづくりを考える会 (2020)
- 『都道府県別災害年表辞典 千葉県』 日外アソシエーツ(2025)
- 3 君待橋の由来について知りたい。
-
『千葉市の散歩道』(2008)によると、昭和44(1969)年3月までは、港町90番地の三叉路のところに「新川」と呼ばれる小さな溝(旧河道)があり、そこに架けられた石橋を「君待橋」といいました。そして昭和55(1980)年、その跡地に「君待橋苑」が設けられ、その北方約200mの都川に新しい「君待橋」が造られたことが分かります。『君待橋記念誌』には、時代につれて変わっていった君待橋の様子が写真とともに掲載されています。
昔の君待橋にはいくつかの伝承があり、『千葉市の民話・伝説・歴史ばなし』『千葉市風土記』や『君待橋物語のリメイク』には、①乙女が若者の後を追い濁流に身を投じたという、はかなくも悲しい物語。
②在原業平と並ぶ、歌人の藤原実方が奥州へ下向する時(955年)に、ここを通りかかり歌を詠んだ。
「寒川や 袖師が浦に 立つ煙 君を待つ橋 身にぞ知らるる」
③千葉常胤が、源頼朝をこの橋のたもとで出迎えた時(1180年)、六男の東六郎胤頼が歌を詠んだ。
「見えかくれ 八重の潮路を 待つ橋や 渡りもあへず 帰る舟人」
という橋の名称に関する3つの伝承が紹介されています。《参考資料》
- 『千葉市の散歩道』 千葉市地域振興課(2008)より、千葉市の散歩道シリーズ⑮名残の港町コース
- 『君待橋記念誌』 千葉市都市改造課(1980)
- 『千葉市の民話・伝説・歴史ばなし』 千秋社(1979)p24-26
- 『千葉市風土記』 千葉日報社(1981)p236-237
- 『日本傳説叢書 下總の巻』 すばる書房(1977)p53-55
- 『君待橋物語のリメイク』 吉野秀夫(2008)
- 『千葉の風景 橋づくし』 森田保(1991)p2
- 『カルチャー千葉 第8号』 千葉市文化振興センター(1985)p201-207
- 『房総の伝説』 暁書房(1975)p10-12
- 2 千葉市の鉄道第一連隊について知りたい。
-
『写真集 千葉市のあゆみ』、『写真集 明治大正昭和 千葉』、『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』、『千葉いまむかし No.3』に、「鉄道連隊の主な任務は、戦地では鉄道の建設・修理・兵員や物資を輸送・敵の鉄道の破壊等であり、平時は千葉市とその周辺で訓練をした。東京の中野にあった鉄道大隊が拡充し、1907(明治40)に一二個中隊からなる鉄道連隊に昇格、第一・第二大隊と材料廠の主力が千葉に移転し大正7年に鉄道第一連隊となった」という内容の記述があります。『回顧四十年[復刻]』は、昭和11(1936)年の千葉の鉄道隊40年記念祭に発刊された資料の復刻版で、鉄道連隊に在職していた隊員たちによる貴重な回顧録です。
なお、鉄道連隊の鉄道線路跡(軽便鉄道線路跡)については、『よつかど No.1』に写真とともに詳しく掲載されています。《参考資料》
- 『写真集 千葉市のあゆみ 第2版』 千葉市広報課(2001)p32-33
- 『写真集 明治大正昭和 千葉』 国書刊行会(1987)p126-127
- 『絵にみる図でよむ千葉市図誌 上巻』 千葉市(1993)p207-210
- 『千葉いまむかし No.3』 千葉市教育委員会(1990)p27-34
- 『千葉いまむかし No.21』 千葉市教育委員会(2008)p11-24
- 『千葉市史 第2巻 (近世近代編) 』 千葉市(1974)p304-305
- 『市民フォトちば 2001春号』 千葉市広報課 (2001) p9
- 『日本陸軍兵科連隊』 新人物往来社(1994)p197
- 『歴史群像2005年6月号』 学習研究社 (2005) p178-185(特集名「陸軍鉄道部隊」)
- 『回顧四十年[復刻]』 鉄葉会(1976)
- 『よつかど No.1』 四街道市郷土史研究会(1984)p31-37
- 『実録鉄道連隊』 イカロス出版 (2009)
- 1 千葉県内の企業の資本金や業績等について調べたい。
-
千葉県内の企業情報については、下記の資料に掲載されています。
『東商信用録 千葉県版』と『東商信用録 関東版 下巻』 と『帝国データバンク会社年鑑 東日本』には企業の資本金・業績・役員名等が載っています。《参考資料》
- 『 東商信用録 千葉県版』 東京商工リサーチ千葉支店(1998-2019)
- 『 東商信用録 関東版 下巻』 東京商工リサーチ東京支社(1988-)
- 『 帝国データバンク会社年鑑 東日本』 帝国データバンク(1994-)
- 『A Level エラベル』 東京商工リサーチ東京支社(1995-)
- 『主要企業要覧 新年特集号 南関東版』 帝国データバンク(2007-2025)
[ここまでが本文です。]